彼女から手編みのマフラーをもらった、という話を聞くと、皆口を揃えて「ええ彼女やね〜」と言う、その「マフラーを編む=家庭的で彼思いの女性」というイメージはどこから生まれてくるのだろう?
という思いから読み始めた一冊が『近代日本の「手芸」とジェンダー』
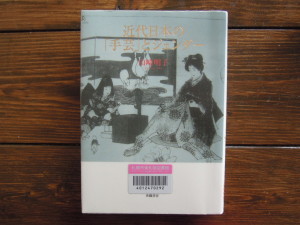
筆者は、大学の博士課程で女性と美術の問題を考え続けるうちに、「手芸」に行き着いたと言います。
美術史や近代史を学ぶ中で、一部染織品を除くと、無数の女性たちが作り出す手芸品は、美術とも工芸とも位置付けられていないことに対する疑問。
「なぜ、モノとしての価値がないにもかかわらず、執拗に女性に手芸を推奨し続けるのか。なぜ、あくまでアマチュアの制作者として作り続けなければならないのか、この不当で矛盾した構造を知りたいというのが、本書の始まりであった」と。
以下、自分の忘備録としてのメモ。
—————————————-
第1章では下田歌子に焦点を当て、「近代国家が女性をいかなる形で統御しうるか」という命題に対して、彼女が具体的かつ実践的な構想を提示し、実際に活動し、近代国家が必要とする女性のあり方を示したことを紹介。
第2章では、「皇后の養蚕」を通して、生産行為であった養蚕が徐々に「手芸」という再生産の文脈に読み替えられていく経緯を紹介。「〜はわが国古来の〜」とか「〜は伝統的な〜」とか、そういう言葉って「で、本当はいつから?」と調べていくと、ホントあてにならない。
第3章では、近代日本の手芸奨励システムとジェンダーについて考察。学校教育、雑誌メディア、博覧会や展示会などによって、手芸が奨励されてきたことが紹介。そうしたシステムによって、「手芸」は全ての階層の女性があたかも「自らの意思で行う」かのように刷り込まれ、強制されてきたのだと。
文中、
美術という言葉が誕生する以前、工芸と芸術の両方のニュアンスを含んでいた言葉として「技芸」(母体は「美術」と同じ)にふれ、近代では「手芸」と「技芸」が極めて近い概念であったこと、手芸が制度化される過程で執拗にジェンダー化しようとする言説が繰り返されたことが紹介。
芸術の内訳が官の枠組みによって類別されていくときに、「手芸」について宮内省と農商務省は、「工芸」と同じくそれぞれ伝統美術、産業品と位置付けているのに、文部省は工芸を芸術、手芸は手芸と位置付けており、
教育の領域で、手芸が明確に芸術と異なるものとして分けられてしまったことが説明されます。
つまり、作り手が女性であった場合、その制作品は「手芸」とも「工芸」とも位置付けることが可能で、これは作り手が男性だった場合には起こらない。と。
さらに、山崎氏は「手芸をめぐる構造は、美術と資本主義と家父長制という三つのシステムの交差する地点にぽっかりと空いた穴のようなもの」とも。
家父長制社会、資本主義経済において、不可欠な女性役割から派生している「手芸」の存在方法について、以下のように説明されます。
一つは家計補助、内職などのように、一家を支えるほどの経済的な恩恵は受けないが、少額でも収入を得る方法。その中で製糸・紡績などは家庭内で女性によって行われるものだったが、代々受け継いできたそれらの技能が明治期に機械化されると、女性は単純かつ低廉な労働力を提供する「女工」として存在せざるを得なかった。
つまり、「産業構造において資本と高度な技術を占有する男性の地位を脅かすことなく、単純な労働と低賃金という条件によって劣等の労働力として期待される」と。
もう一つは、家庭の妻として、母として、家庭内において無償の労働として行われる方法。
「市場価値のないものをひたすらに生産し続ける行為は、基本的に無償である育児や家事に専念することをもって婦徳とする家父長制社会の女性規範の一つ。また、市場価値のないモノを生産することを許すということが、その女性を扶養している男性の経済力の高さや属する階級の証明でもあった」。
「手芸」とは家庭内において家族のために行う手仕事であると、明治期のイデオローグによって繰り返し説かれた。同時に「手芸」の技能を有していれば、万一の場合、いくらかの生活の糧を稼ぐことができるとも繰り返された。この二つの言説は、中産階級の女性が置かれた社会状況の表裏の位置にあるもので、彼女たちが常に自らの脆弱な財産基盤を意識しながら、また、転落への危機を喚起されながら生きて行かざるを得なかったことを示している。
さらに
手芸を行うことによって、女性は自らの身体を矯正する。同時に、手芸によって女性領域を遵守するとともに自らの女性性を示すことが可能になる。こうした身体的矯正と精神の陶冶は、明治期を通じて女性たちを「不払い」の「生産」行為である「手芸」行為へと回収する効率的なシステムとなっていた。
「手芸」は社会的文脈を剥ぎ取ってみれば、明らかに生産労働であると言うことができる。でも、あたかも再生産労働であるかのように偽装されてきた。つまり、近代におけるジェンダー規範は、基本的には女性を家庭内におくべき存在としながらも、安価に緻密な単純作業を行うための人員を確保するために、女性たちに常に高度な生産技能を修得させ、その技能を維持させ続けるためにこれらの社会的文脈が必要だった。
このような「手芸」の国家的奨励は、女性の文化創造のエネルギーを家庭内での女性役割に吸収し、その精神と身体を統御するための巧妙なシステムであったと言えよう。
——————–
自分は服作りをするけど、それは「自分が履きたい型と色と素材のズボンがないから、自分で作る」という、自己中心的な理由のみで作っているので、もう全然国家が(未だに)推奨するような女性像ではない…。いいけど。
冒頭の自身の問いに遡ると、まあイメージが昔ながらなだけに「むむ、この思考回路は…」と思ったけど、現代の価値観からしても「好きな人のために自身の創造性を発揮する人は、男女関係なく素敵だ」と思う回路は、あまり社会的文脈とか関係ないかも。
でも、それを「家庭的」と思う回路は、そう位置付けられていった背景を知ると、あまり使いたくない気も。あくまで「手を動かして何かを作ることと、あなたのことが好きなのね」でとどめたい。
という結論です。編み物でも、料理でも、何でも。
自分も次に誰かを好きになったら、古典的なジェンダーイメージとは関係なく、「好きな人のために自身の創造性を発揮する」という至極真っ当なことをたくさんしたいな〜。
それにしても「手芸」ということにちょっと戻ると、国家が女性を統御するために推奨した結果としての例えば「刺繍」と、アイヌに伝わる「刺繍」とでは、行為に含まれるものが違うのかな。アイヌの女性が刺繍をするとき、そこに身体的矯正や精神の陶冶はあるのだろうか。あるとしたら、それは誰が望んで?
この辺、ちょっと他の本を読んでみたい。
あとはー
本書を読んでさらに興味が強まったトピックは、やっぱり、「国家」「社会的文脈を作るための言説(読み替えを含む)」かなあ。
いろんな女性誌の「煽り具合」と「煽ってる方向性(それを支持する読者像)」を読み比べるのが好きなのですが、「女性」を取り巻く言説というのは、本当に大変ですよね。me tooとか、プラスサイズ・モデルとか、アルヴィダ・バイストロムとか、文脈をどんどん変えていってほしいな〜と思いますけども。
それにしても
自分が生きてきた41年間のうちに、いろんな言葉を内面化してしまっているから、自分が「本当に」望んでいることを発見するには、もう直感とか、潜在意識とか、その辺が一番正直なのかもしれないですねえ。
と、尻切れトンボで終わる。
(編)
旧ブログ
(編)のつぶやき
アーカイブ
- 2026年3月 (2)
- 2026年2月 (9)
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (6)
- 2025年11月 (7)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (10)
- 2025年8月 (9)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (6)
- 2025年5月 (16)
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (6)
- 2025年2月 (8)
- 2025年1月 (5)
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (6)
- 2024年10月 (7)
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (6)
- 2024年7月 (8)
- 2024年6月 (4)
- 2024年5月 (18)
- 2024年4月 (6)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (11)
- 2024年1月 (6)
- 2023年12月 (9)
- 2023年11月 (10)
- 2023年10月 (5)
- 2023年9月 (10)
- 2023年8月 (12)
- 2023年7月 (20)
- 2023年6月 (11)
- 2023年5月 (13)
- 2023年4月 (5)
- 2023年3月 (9)
- 2023年2月 (12)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (12)
- 2022年11月 (5)
- 2022年10月 (11)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (9)
- 2022年6月 (7)
- 2022年5月 (6)
- 2022年4月 (5)
- 2022年3月 (5)
- 2022年2月 (5)
- 2022年1月 (4)
- 2021年12月 (9)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (8)
- 2021年9月 (5)
- 2021年8月 (8)
- 2021年7月 (6)
- 2021年6月 (9)
- 2021年5月 (11)
- 2021年4月 (5)
- 2021年3月 (9)
- 2021年2月 (7)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (7)
- 2020年11月 (15)
- 2020年10月 (12)
- 2020年9月 (8)
- 2020年8月 (7)
- 2020年7月 (10)
- 2020年6月 (17)
- 2020年5月 (17)
- 2020年4月 (8)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (11)
- 2020年1月 (9)
- 2019年12月 (10)
- 2019年11月 (15)
- 2019年10月 (12)
- 2019年9月 (13)
- 2019年8月 (13)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (5)
- 2019年5月 (24)
- 2019年4月 (13)
- 2019年3月 (13)
- 2019年2月 (15)
- 2019年1月 (6)
- 2018年12月 (11)
- 2018年11月 (9)
- 2018年10月 (9)
- 2018年9月 (5)
- 2018年8月 (9)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (26)
- 2018年5月 (13)
- 2018年4月 (7)
- 2018年3月 (9)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (6)
- 2017年12月 (7)
- 2017年11月 (6)
- 2017年10月 (6)
- 2017年9月 (18)
- 2017年8月 (15)
- 2017年7月 (10)
- 2017年6月 (30)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (7)
- 2017年3月 (6)
- 2017年2月 (12)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (7)
- 2016年11月 (19)
- 2016年10月 (8)
- 2016年9月 (11)
- 2016年8月 (9)
- 2016年7月 (21)
- 2016年6月 (12)
- 2016年5月 (9)
- 2016年4月 (18)
- 2016年3月 (15)
- 2016年2月 (9)
- 2016年1月 (8)
- 2015年12月 (9)
- 2015年11月 (23)
- 2015年10月 (21)
- 2015年9月 (17)
- 2015年8月 (20)
- 2015年7月 (28)
- 2015年6月 (26)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (22)
- 2015年3月 (22)
- 2015年2月 (23)
- 2015年1月 (22)
- 2014年12月 (32)
- 2014年11月 (39)
- 2014年10月 (19)
- 2014年9月 (25)
- 2014年8月 (33)
- 2014年7月 (24)
- 2014年6月 (29)
- 2014年5月 (31)
- 2014年4月 (22)
- 2014年3月 (29)
- 2014年2月 (35)
- 2014年1月 (27)
- 2013年12月 (35)
- 2013年11月 (31)
- 2013年10月 (22)
- 2013年9月 (28)
- 2013年8月 (23)
- 2013年7月 (31)
- 2013年6月 (37)
- 2013年5月 (30)
- 2013年4月 (24)
- 2013年3月 (27)
- 2013年2月 (20)
- 2013年1月 (20)
- 2012年12月 (28)
- 2012年11月 (42)
- 2012年10月 (30)
- 2012年9月 (23)
- 2012年8月 (13)
- 2012年7月 (31)
- 2012年6月 (25)
- 2012年5月 (32)
- 2012年4月 (28)
- 2012年3月 (29)
- 2012年2月 (26)
- 2012年1月 (26)
- 2011年12月 (27)
- 2011年11月 (20)
- 2011年10月 (33)
- 2011年9月 (32)
- 2011年8月 (34)
- 2011年7月 (38)
- 2011年6月 (39)
- 2011年5月 (33)
- 2011年4月 (31)
- 2011年3月 (30)
- 2011年2月 (30)
- 2011年1月 (30)




